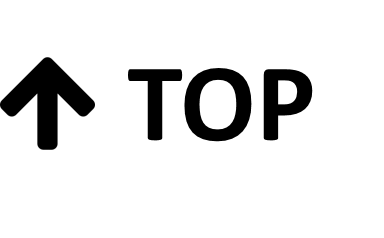FDCD-465 型 高感度 FDCD 測定装置を用いた測定例の紹介
円二色性(CD)測定法は、低分子の絶対構造の決定や、生体物質の構造やそれらの相互作用に関する知見を得るための有力な方法として知られています。CD は光学活性物質が示す左右の円偏光に対するモル吸光係数の差であり、以下の(1)式のように表現されます。
Δε = ε1 - εr (1)
このような光学活性物質が蛍光性を有する場合、その蛍光性光学活性物質は CD だけでなく、左右の円偏光で励起した時の蛍光強度にも差を示します。左円偏光と右円偏光で励起した時の試料の蛍光強度をそれぞれ Fl, Fr とすると、その差は以下の(2)式のように表現されます。
ΔF = Fl - Fr (2)
このような光学活性物質が示す蛍光強度の差を測定する手法は、蛍光検出 CD (FDCD : Fluorescence Detected Circular Dichroism) と呼ばれています。
一般に試料の吸光度も蛍光強度も濃度に比例して増大していきます。つまり試料の吸光度と蛍光強度も比例関係にあると言えます。光学活性物質では左右円偏光に対する吸収の差が大きくなれば蛍光強度の差も比例して大きくなることになります。そのため、励起させた発色団から他の発色団へのエネルギー移動が無視できる系であるなら、左右円偏光によって試料を励起してその時の蛍光強度の差を測定することにより、左右円偏光に対する吸収の差、すなわち CD に換算できることになります。この時の CD と FDCD の関係は以下の(3)式のように得られています。
Δε = ε1 - εr = (3.032×10-5)×S×(1-10-A)/(cd10-A) (3)
A:試料の吸光度 c:試料のモル濃度(M) d:セル長(cm) S:実測の FDCD 値(mdeg)
実測の FDCD 値 (mdeg) は、S = 28648×(Fl-Fr)/(Fl+Fr) という計算によって得られており、トータルの蛍光強度に対する左右円偏光で励起した時の蛍光強度の差として評価されています。上記の 28648 は観測された蛍光強度の差を mdeg の単位に変換するための定数です。
この定義は、1974 年に Turner 先生らが最初に提唱された FDCD の定義と逆になっていますが、1997 年に中西先生らが CD 励起子キラリティー法と FDCD 測定法を組み合わせた高感度測定法について報告された際に、通常の CD の定義と符合が一致するよう改められたものを採用しています。
FDCD は原理的に蛍光性発色団の CD のみを選択的に観測します。そのため、複数の発色団に由来する CD スペクトルが重なり合う場合に、そこから蛍光性発色団に由来する CD スペクトルのみを選択的に検出することができます。
また、分光蛍光光度計は分光光度計に比較して高感度であることが一般に言われていますが、UV 検出が通常の CD、蛍光検出が FDCD に相当するので、蛍光性を有し、量子収率が高い、FDCD に適した試料であるなら FDCD は CD 以上の高感度測定が可能となります。ここでは、高感度型 FDCD 測定装置 FDCD-465 を用いた測定例を紹介します。