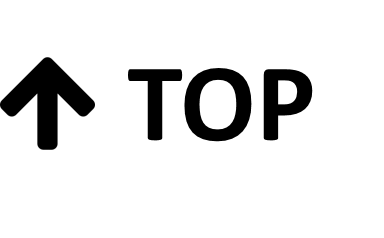クロマトグラフィー・破過曲線の理論予測に向けての熱力学×化学工学(熱力化学工学)に基づく移流-平衡段モデルの検証
2021年・令和3年春に、クロマトグラフィーを理論予測するための「熱力学に基づく吸着平衡」と「化学工学に基づく物質収支」に立脚した新しい数理モデルを、Excelシート上で独自に開発してから3年半ほどが経過した。この間、修士課程の研究テーマとして取り組んでくれた共著者の松田 修汰 氏や、卜部 真聖 氏と議論を重ねたこの理論モデルも、2023年の和文論文誌・化学工学論文集の速報1)を経て、2024年の国際誌・Chromatography誌のオリジナル論文2)にも無事掲載され、ようやくこのモデルをこうして紹介できるようになった。この機会にこれまでにまとめきれなかった内容を詳しく紹介できれば誠にありがたい。まずは冒頭にて、執筆の機会をいただいた日本分光株式会社関係各位に深く感謝を申し上げたい。
本稿には、先に述べた化学工学論文集1)や Chromatography 誌2)に掲載された論文の解説記事としての意味合いがある。また、この機会をお借りして、構築した理論を論理的に検証したいとも考えており、Microsoft Excel での計算例をもとに議論を進められたら幸いである。最終的には、人間の経験に基づき構築されきたクロマトグラフィーに対し、著者らの理論を適用・拡張させることで、ソフトウェアの開発など社会実装に貢献できればと考えている。
既往のクロマトグラフィー計算モデルの紹介
独自に開発した数理モデルを紹介する前に、既往の研究を整理する。
クロマトグラフィー実験において、対象溶質を効率よく分離するためには、充填カラムの固相部分に相当する固定相と、カラム空隙部分に相当する移動相の特性を最適化する必要がある。ここで、この最適化に関与する操作条件・操作因子をまとめると、温度、圧力、溶媒組成・流量、溶質濃度・仕込量といった移動相特性に加えて、カラム充填剤の固定相特性(粒径、粒子数、表面積、表面官能基の種類・修飾率、多孔度、カラム内空隙率)が挙げられる。従来、これら操作条件・操作因子の最適化には経験則(経験的実験)が用いられてきているが、一般に試し実験には手間と時間とコストがかかるので、理論に基づき数学的に処理できれば(理論予測できれば)有用と考えられる。著者らの研究グループは、正にその高み・極みを目指しつつ、日々の研究活動を推進している。
このような背景のもと、東京工業大学(現 東京科学大学)伊東 章 先生らの成書「Excelで気軽に化学工学」3)によれば、従来のクロマトグラフィーの理論モデルとして「完全混合槽列モデル」や「移流拡散モデル」が紹介されている。前者は、クロマトグラフィーの現象を、単段の完全混合槽がカラム軸方向に連なった槽列として抽象化しているのに対し、後者は、溶質が系内にパルス的に添加された後の移流と拡散によるクロマトピークの遷移を数学的に記述している。ここで、これら問題の解法に着目すると、前者では、一般に時間に対する常微分方程式の解法が適用されるのに対し、後者では偏微分方程式の解法が必要となり、計算上、拡散係数や物質移動係数などの輸送パラメータが必要となる。紙面の都合により、ここで紹介した内容についてのさらに詳しい解法に関しては、伊東先生らの成書3)を参考にしていただきたい。
その一方で、ここで紹介した既往の研究以外にも、クロマトグラムのピークトップ位置(保持係数)を独自のシステムパラメータから予測するAbrahamモデル4)や、溶質のモビリティー(拡散現象)の視点からピーク幅を議論する「Taylor Dispersion Method」なる方法論5)も提案されている。後者は、特に、船造 俊孝 先生らのReview論文中によくまとめられているので、この機会にこちらもご紹介申し上げたい。このほかクロマトグラムの計算には、これらのモデルとは別に、理論段モデル6)なども広く利用されている現状があり、これら数理モデルは、我々独自のモデルを展開する上で基礎となったことは間違いない。
要するに、クロマトグラムの計算には、実に多くのアイディアが含まれることに今更ながら気付く。これ以降も理論や学理の拡がりは決して止むことはないものと予想される。
1) 大田昌樹,松田修汰,平賀佑也,渡邉賢,猪股宏,化学工学論文集, 49, 129-132 (2023).
2) Masaki Ota, Masato Urabe, Yoshiya Matsukawa, Hiroyuki Komatsu, Masaru Watanabe, Chromatography, 45, 101-106 (2024).
3) 伊東章, 上江洲一也, Excelで気軽に化学工学, 丸善 (2006).
4) Michael H. Abraham, Priscilla L. Grellier, Ian Hamerton, R. Andrew McGill, David V. Prior, Gary S. Whiting, Faraday Discuss. Chem. Soc., 85, 107-115 (1988).
5) Toshitaka Funazukuri, Chang Yi Kong, Seiichiro Kagei, Journal of Chromatography A, 1037 411-42 (2004).
6) J. J. Baeza-Baeza, M. C. García-Álvarez-Coque, Journal of Chromatography A, 1218, 5166-5174 (2011).