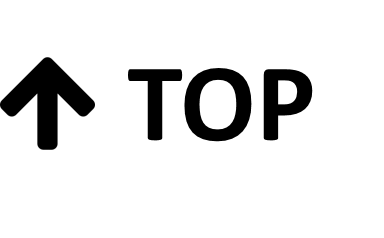エピジェネティック修飾が核酸の高次構造に与える影響
我々の体は約 37 兆個の細胞から構成されており、その種類は約 200 種類と言われている。この膨大かつ多様な細胞は、もともとは1つの細胞、つまり受精卵から発生したものである。受精卵から各細胞に発生する過程で、ゲノムDNAは正確に複製される。そのため、同一個体内ではすべての細胞が基本的には同じゲノムDNAを持つが、各細胞・組織ごとに機能が異なる。同じゲノムDNAを持つ細胞がなぜ異なる機能を発揮するのだろうか。それは、発現している遺伝子が異なるからである。ヒトゲノムDNAには約2万個の遺伝子が含まれているが、一つの細胞の中ですべての遺伝子が発現していることはなく、遺伝子の発現パターンは組織特異性がある。この遺伝子の発現パターンを決める要因の一つがエピジェネティック修飾である。エピジェネティクスは「DNAの配列変化を伴わずに子孫や娘細胞に伝達される遺伝子機能の変化と、この現象を探求する学問」と定義されている1)。エピジェネティクスの主要な制御機構の一つに DNA のメチル化がある。
DNA メチル化とは主にシトシンとグアニンの連続配列(CpG)中のシトシンの5位がメチル化されて5-メチルシトシン(5mC)になる反応のことである2)。30 億塩基で構成させるヒトゲノム DNA には約 2800 万箇所の CpG 配列が含まれている3)。ゲノム DNA 中の CpG がメチル化されると、Methyl-CpG binding proteins などによりヒストン修飾酵素やクロマチンリモデリング因子がリクルートされ、その領域でヘテロクロマチンが形成される。そのため、プロモーター中の CpG がメチル化されると、一般的にはその遺伝子の発現が抑制される。つまり、CpG のメチル化は遺伝子発現を制御するスイッチとして機能している。実際に、発生の過程において、組織特異的なメチル化パターンが形成される。また、体細胞から iPS 細胞を作製すると、ES 細胞と類似したメチル化パターンが形成されることも報告されており、メチル化パターンは細胞の特性を決定するマーカーともなる4)。
ヒトゲノムDNA中に含まれる修飾塩基としては、5mC 以外にも、脱メチル化反応の中間産物である5-ヒドロキシメチルシトシンや5-ホルミルシトシン、5-カルボキシシトシンなどが同定されている5), 6)。また、RNA も様々な修飾を受けており、RNA 中で最も豊富に存在する修飾塩基はアデニンの6位がメチル化されたN6-メチルアデニン(m6A)である7)。m6Aには、メチル基がN1サイドに位置するcis型と、メチル基がN7サイドに位置するtrans型の2つの回転異性体が存在する8), 9)。cis型とtrans型の形成割合は19:1であり、cis型の方が優位に形成される。cis型では、このメチル基がチミンとのワトソン・クリック塩基対形成を阻害することから、mRNAの二次構造がm6A修飾により変化し、スプライシングが制御されていることが報告された10)。つまり、修飾塩基による核酸の高次構造形成制御により、生命現象が制御されていることが明らかになった。
DNAは通常二重らせん構造を形成するが、ステムループや三重鎖、グアニン四重鎖(G-quadruplex:G4)、i-モチーフ(intercalated motif:i-motf)などの非二重らせん構造も形成する11)。G4構造とは連続した4つのグアニン間で形成される平面構造(Gカルテット)がスタッキング相互作用により、積み重なって形成される構造である。G4構造形成にはイオンが必要であり、K+はGカルテット間に、Na+はGカルテット内に配位することでG4構造を安定化する。G4構造はそのストランドの向きから、①パラレル型、②アンチパラレル型、③ハイブリット型、の3つに分類される。また、GGAが4回繰り返されたリボヌクレオチド(r(GGA)4)はGカルテットとG(:A):G:G(:A):G hexad構造を含む特殊な二量体化G4構造を形成する。i-motif構造とはプロトン化シトシン(C+)とシトシン間で形成される塩基対が互い違いに重なって形成される構造である。i-motif構造が形成するためにはシトシンのプロトン化が必要であるため、通常i-motifは酸性条件下で形成する。
ゲノムDNAにおいてG4構造形成配列はグアニンが豊富な領域に含まれており、その相補鎖にi-motif構造形成配列が含まれている。ヒトゲノムDNAにおいて、G4構造形成モチーフ(G3N1-7G3N1-7G3N1-7G3)は転写開始点近傍に多く含まれている12)。実際にG4構造に特異的に結合するリガンドとDNAマイクロアレイや次世代シークエンサーを用いて、ヒトゲノムDNA中に含まれるG4構造形成配列を網羅的に解析した結果、G4構造形成配列が転写開始点近傍に多く含まれていることが明らかになった13)‐15)。そのため、G4構造形成が転写制御に関与していることが示唆されるが、二重らせん構造からG4構造やi-motif構造形成が誘起されるメカニズムは不明な点が多い。
筆者はCpG中の5mCやm6A修飾により、核酸の高次構造形成が制御されているのではないかと考え、研究を進めてきた。メチル基は電子供与体であるため、シトシンの5位がメチル化されるとピリミジン環の電子密度が上昇する。その結果、近傍の塩基とのスタッキング相互作用が増強される16)。また、メチル化によりC-C+塩基対が安定化することも報告されている17)。m6Aはメチル基により近傍の塩基とのスタッキング相互作用が増強される一方、上記の通り、ワトソン・クリック塩基対形成が阻害される18)。そのため、これら修飾塩基を含む核酸が形成する高次構造の熱安定性を精密に測定することで、これら修飾塩基が核酸の高次構造形成に与える影響を明らかにすることができる。
核酸の高次構造を解析する方法としては、DMSフットプリント法、円二色性(Circular Dichroism: CD)スペクトル解析法、NMR法、X線結晶構造解析法などが挙げられる。これらの中で最も簡便に解析を行うことができる方法がCDスペクトル解析法である。特にG4構造やi-motif構造は特有のCDスペクトルを示すことから、簡便かつ精密にその構造の熱安定性を測定することが可能である。また測定が簡便であるため、種々の条件での測定が可能であり、核酸の高次構造解析において重要な解析方法となっている。そこで、本稿ではCDスペクトル解析法を用いた修飾塩基が核酸の高次構造に与える影響を解析した結果を解説する。
1) C. Wu and J. R. Morris, Science, 2001, 293, 1103-1105.
2) M. V. C. Greenberg and D. Bourc’his, Nat. Rev. Mol. Cell Biol., 2019, 20, 590-607.
3) Z. D. Smith and A. Meissner, Nat. Rev. Gent., 2013, 14, 204-220.
4) R. Lister, M. Pelizzola, Y. S. Kida, R. D. Hawkins, J. R. Nery, G. Hon, J. Antosiewicz-Bourget, R. O’Malley, R. Castanon, S. Klugman, M. Downes, R. Yu, R. Stewart, B. Ren, J. A. Thomson, R. M. Evans and J. R. Ecker, Nature, 2011, 471, 68-73.
5) M. Tahiliani, K. P. Koh, Y. Shen, W. A. Pastor, H. Bandukwala, Y. Brudno, S. Agarwal, L. M. Iyer, D. R. Liu, L. Aravind and A. Rao, Science, 2009, 324, 930-935.
6) S. Ito, L. Shen, Q. Dai, S. C. Wu, L. B. Collins, J. A. Swenberg, C. He and Y. Zhang, Science, 2011, 333, 1300-1303.
7) F. Qu, P. S. Tsegay and Y. Liu, Front. Mol. Biosci., 2021, 8, 645823.
8) J. D. Engel and P. H. von Hippel, Biochemistry, 1974, 13, 4143-4158.
9) J. D. Engel and P. H. von Hippel, J. Biol. Chem., 1978, 253, 927-934.
10) N. Liu, Q. Dai, G. Zheng, C. He, M. Parisien and T. Pan, Nature, 2015, 518, 560-564.
11) R. C. Duardo, F. Guerra, S. Pepe and G. Capranico, Biochimie, 2023, 214, 176-192.
12) J. L. Huppert and S. Balasubramanian, Nucleic Acids Res., 2005, 33, 2908-2916.
13) K. Iida, T. Nakamura, W. Yoshida, M. Tera, K. Nakabayashi, K. Hata, K. Ikebukuro and K. Nagasawa, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 2013, 52, 12052-12055.
14) V. S. Chambers, G. Marsico, J. M. Boutell, M. Di Antonio, G. P. Smith and S. Balasubramanian, Nat. Biotechnol., 2015, 33, 877-881.
15) W. Yoshida, H. Saikyo, K. Nakabayashi, H. Yoshioka, D. H. Bay, K. Iida, T. Kawai, K. Hata, K. Ikebukuro, K. Nagasawa and I. Karube, Sci. Rep., 2018, 8, 3116.
16) L. C. Sowers, B. R. Shaw and W. D. Sedwick, Biochem. Biophys. Res. Commun., 1987, 148, 790-794.
17) B. Yang and M. T. Rodgers, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 282-290.
18) C. Roost, S. R. Lynch, P. J. Batista, K. Qu, H. Y. Chang and E. T. Kool, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 2107-2115.