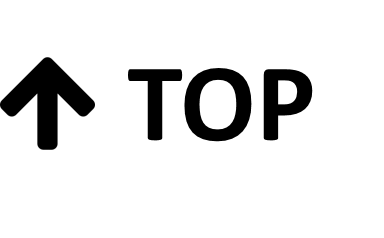真珠に現れる色の測定と鑑別への応用について
真珠は、貝殻をつくる機能を持つ貝の器官である外套膜の細胞が、貝体内で作り出した物質で、その成分・構造は貝殻と同じです。真珠層構造である真珠に現れる色は、その貝特有の色素の色とその構造から現れる干渉色が重なり見えるため複雑ですが、分光光度計でこの特有の色素の特徴を確認することで、どの種類の貝から採れた真珠かの判別をすることができることがあります。また、各種分光光度計の測定によって、漂白、着色などの処理の判断基準のひとつを得ることができます。
真珠の成因
さまざまな貝は、外套膜という器官の働きにより貝殻をつくります。その貝殻を構成する構造1)は、真珠層構造、稜柱層構造、交差版構造、粒状構造など貝の種類によって異なります。そして、何らかの原因で貝体内に外套膜片が入り細胞が増殖して袋状になった時、その袋の中に貝殻と同じ構造の物質を作ります。袋状の組織を真珠袋と呼び、できた物質を真珠と呼んでいます2)。人の手で外套膜片を貝体内に入れて作られるのが養殖真珠、偶然真珠袋ができて作られたのが天然真珠です。貝の種類によって作ることのできる構造が異なりますので、厳密には真珠層構造を持つ貝のみが真珠を作り出します。ただし、実際にはコンクパール、クラムパールなどのように、真珠層構造を持たないものも真珠として流通しています。真珠養殖に用いられる真珠層構造を持つ貝は、アコヤガイ、クロチョウガイ、シロチョウガイ、マベ、アワビなど海水で生息する貝と、イケチョウガイ、ヒレイケチョウガイなど淡水で生息する貝があります。
真珠の色
真珠層構造は、アラゴナイトの炭酸カルシウムの層とタンパク質の層が交互に積み重なった構造をしており、タンパク質層には各種の貝特有の色素が含まれています。また、200~500 nm 程度の厚さの層が積み重なった時に光の干渉が起こり、現れる干渉色は結晶層の厚さと球体上の位置によって変わります3)。この色素の色と干渉色が同時に現われるため、真珠の色は複雑です。
1) 魚住悟, 鈴木清一(1981):「二枚貝における殻体構造の進化」, 軟体動物の研究, 大森昌衛教授還暦記念論文集, 63-78
2) 和田浩爾(1999):「真珠の科学」, 第2章 外套膜と真珠袋の構造と働き, 33-68
3) 小松博(2015):「真珠事典」, Ⅴ品質, 50-62